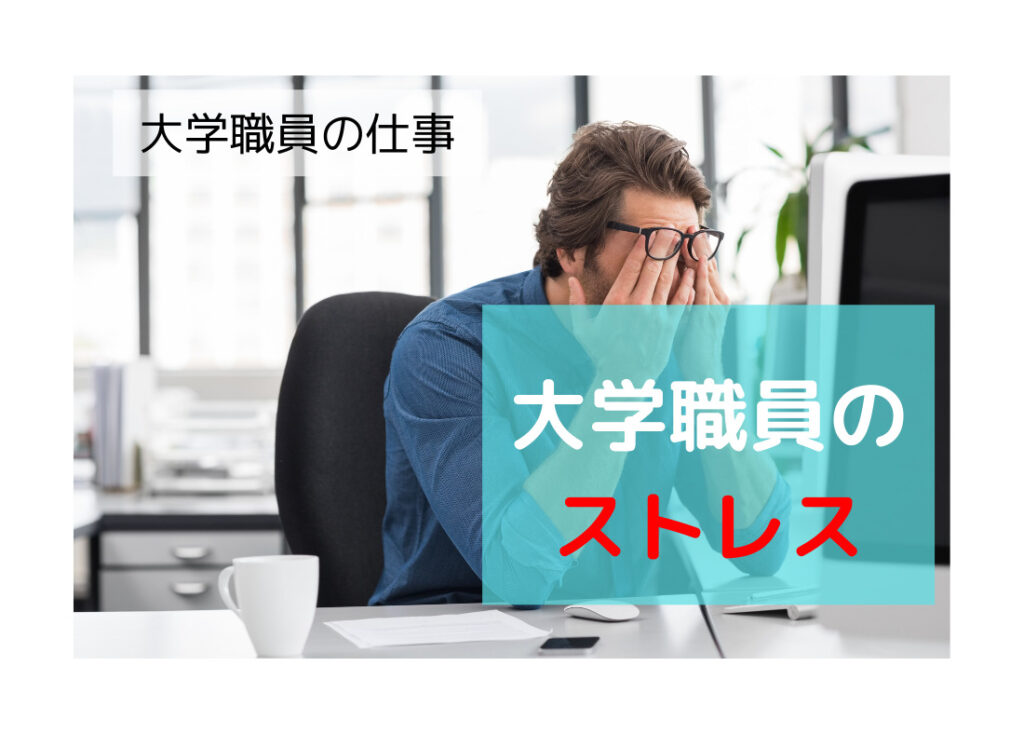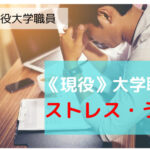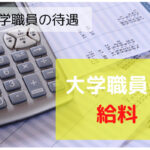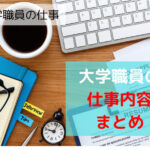「大学職員ってストレスなんてあるの?」
「現役だけど大学職員つらい・・・」
このように思われている方もいるのではないでしょうか。
今回は大学職員のストレスについて紹介していこうと思います。
この記事でわかること
- 大学職員のストレス
- 仕事に対する意識から起こるストレス
- 人間関係から起こすストレス
- 教員との関係から起こるストレス
- 仕事のプレッシャーから起こるストレス
- パワハラはある?
- うつや休職者はいる?
- 転職者がストレスに感じること
先に結論を言っておくとストレスはあります。
今勤められている企業でもストレスはありますよね。一緒です。
大学職員特有のストレスも存在しますが、普通にストレスはあると思って入職していただければ大丈夫です。
またこの記事を読んでいただければどういった人が大学職員として好まれるのか、転職の参考にもなるはずです。
現役大学職員でストレスに悩まれている方はこちら▼
-

つらいですよね。今現役大学職員でうつやストレスに悩んでいる休職や退職を考えている方へ
今回は、今現役大学職員でうつやストレスに悩んでいる方へこの記事は書いております。 大学職員への転職を考えている方向けではありませんのでご了承ください。 実は大 ...
続きを見る
このサイトでは大学職員の本当の実情を知った上で転職してほしいため、シビアに情報を発信しています。
\ ▼まずは求人を探してみる▼ /
おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
大学職員はストレスある?
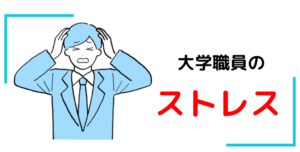
あります。
社会人の常識を持っている方、意欲がある人ほどストレスを感じるのが大学職員です。
逆に「言われたことをやる」というのが性にあっている人には最高の職場です。ストレスはあまり感じないと思います。
ではどのような場面でストレスを感じるのでしょうか。
具体的にいえば
①職場の仕事に対する意識
②職員同士の人間関係
③教員との関係
④仕事のプレッシャー
この4点がストレスを感じる原因になることが多いです。
大学職員特有の文化が多く存在します。
\ ▼まずは求人を探してみる▼ /
おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
①職場の仕事に対する意識(前例主義)からのストレス
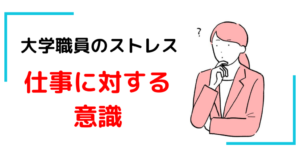
基本大学職員は前例主義、変わらないことをよしとする文化です。
目的から仕事をすることがありません。
「去年していたからした」が口癖です。
これはどの大学も程度の差はあれ、根本は変わらないと断言できます。
そのため、何かを変えようとすると、とてつもない労力がかかります。
企画書を上長に提出しても、責任の所在が曖昧なため、必ずといっていいほど会議を開き、会議を重視します。
またやっかいなのが、その会議でも責任の所在があいまいになり、決まらないということが往々にしてあります。
会議の口癖として「では次までにまた検討するということで」というのがあります。
いつになったら決まるのか、本当にわからないです。
スピード感はまるでありません。
時間を失っているという認識はありません。時間はいくらでもあるという認識です。
そのためちゃんと変えていこうとする意識を持っている人からすれば、拷問のような職場となります。
大学職員として学生のためによくしようと、ちゃんとした人ほど、ストレスを抱える人も多いのが大学職員です。

\ ▼まずは求人を探してみる▼ /
おすすめ転職サイト
【正社員を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
②人間関係が閉鎖的なことによるストレス
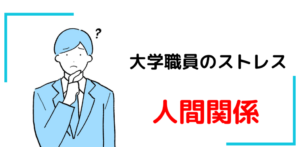
ストレスを一番感じるのは、やはり人間関係です。
大学職員は根が真面目な人が多く、ルールを絶対順守の雰囲気があります。
「チャレンジ」より「調和」を大事にします。
暗黙のルールを破ると異常なほど攻めてきます。
また真面目同士がぶつかるため、シンプルに職歴が長い人が言うことが正しい雰囲気があります。
間違っているとわかっていても、真面目なため意見を述べる職員は多くなく、ただいわれるがままになります。
それがストレスにつながる人が多いです。

おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
大学職員が閉鎖的な理由
なぜそのような文化があるかと考えると、広報関係の部署以外は基本、他大学含め外部の人と交流する機会がほぼないです。
また世間が今どのようなことになっているか政治・経済を気にする人もほとんどいません。
新しい情報・世間の潮流を取り入れる必要がなくてもやっていけます。
そのため、人生においても内部で人間関係が完結する人がほとんどとなり、新しい考え方が入ってきにくい職場です。
そうなってくると、昔からある職場の考え方が絶対(常識)となっていき、長くいればいるだけ自分の意見が絶対だという職員が増えます。
若い頃は反発する人もいますが、上司や先輩からそれは本学の考え方ではないと、事あるごとに矯正されていきます。
そのうち若い人も「言っても意味がない」とあきらめていきます。
考えることをやめていきます。流されていきます。
すると不思議なもので、また新しい昔の考え方を絶対視する職員が生まれます。
自分も若い頃そういわれてきた!とまた同じループになっていきます。
何人もそのような方を見てきました。

おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
実例
実際管理人の大学でも、前職でバリバリ営業系だった方が転職してきました。
こういうやり方もどうですか?とよく提案してました。
中身を見ても、とてもいい企画をたくさん提案していました。他課ではありましたが、私もよく相談にのりました。
しかし新しいことへのチャレンジは関わりたくない、否定する人が多く、年々やる気をなくしていってました。
「提案しても意味がないですもんね・・・」とやる気をなくしていく姿は本当に悲しかったです。
やっかいなのが、1対1で言うのではなく、職場全体の雰囲気として、「あの人は間違っている」雰囲気を出してきます。
「余計なことをする人」という認識になっていきます。
管理人の大学だけかなと思い、周りの大学職員の方と以前飲み会のときに聞いてみたら、どこも程度の差はあれば、同じような雰囲気とのことでした。

\ ▼まずは求人を探してみる▼ /
おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
③教員との関係によるストレス
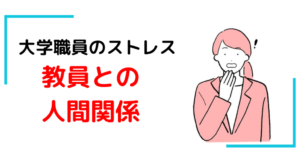
大学は教員と大学職員と異なる職種の人間が混在します。
大学職員と大学教員は「車の両輪」などと例えられますが、基本は大学職員より教員の方が立ち位置は上です。
大学職員も教員が言うことは絶対服従と考えている人が多いです。
実際は教員はあくまで特定の分野に秀でているだけなので、その他の分野はびっくりするほど得意ではありません。
そのため、教員から変な指示が出されることも多いです。
しかし教員様の言うことは聞かなければと矯正されているので、変な指示に従います。
教員に常識は通じません。
締切の概念もありません。
決められたことを守るという概念も薄いです。
生え抜き職員は教員のいうことは絶対と教育されてきているので違和感ない人が多いですが、転職者はここは大きくストレスを感じる部分のようです。
教員と転職者では、言ってることは転職者の方が正しいことが多いです。

\ ▼まずは求人を探してみる▼ /
おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
④仕事のプレッシャーによるストレス(成果を求められる・クレーム対応等)
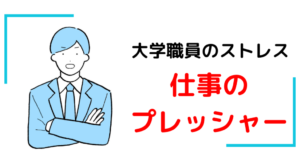
よくもわるくも大学職員は「事務職員」の側面がまだ強いです。
そのため「決められたこと」を「決められた方法でやる」ことは得意です。
代わりに「責任を持って」「創造性を活かして成果を出す」ことがとても苦手です。

責任を持つことによるストレス
大学職員の仕事での口癖は「去年やっていたからした」「去年こういったやり方をしていたからそうした」です。
仕事の目的から「やるべき」「やらないべき」「仕事やり方」を選択できる人は私も数人しか見たことがないです。
トラブルが起きたときは面白いです。
上司「なんでこんなことになったの?」
部下「去年のやり方通りしました」
上司「でもトラブル起こるのわかってたでしょう?」
部下「私は去年の通りしました。わかりません!これ以上はできません!」
これが通じる世界です。
事前にリスクがあるとわかっていたとしても前年通りのやり方を選択する人が多いです。
また上司・部下含め「わからない」「できない」が平気で通じる世界です。
「去年やっていた」という言葉で、責任は自分にないというスタンスです(自分は去年通りやっているので、このやり方を発明した昔の担当者が悪い。)。
このような文化があるのが大学職員なため、急に「この仕事は君の責任でやるんだ」と言われると、ストレスが強くなり、拒絶反応を起こし、体調不良になる人を何人も見ました。
決して大きなプロジェクトではなく、平社員が十分やれる範囲の仕事でもプレッシャーを強く感じる人は多いです。
転職してきた人たちが「え?この程度の仕事でプレッシャー感じるの??」とびっくりするところですね。
おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
成果を求めることによるストレス
社会人としては「給料」という対価をもらっているので、「成果」で返すのは当たり前だと思います。
しかしこの当たり前は大学職員には通用しません。
大学職員は「事務」は得意な人が多いですが、「成果を発生させる」ことは苦手です。
具体的には募集部門(入試・広報関連)等がそこに該当します。
入試・広報関連部署は大学職員の中で数少ない「成果」を求められる部署です。
また他の部署に比べ、外部(受験生等)に対する「責任」も大きく発生します。
そのため、入試・広報関連部署は大学職員で最も人気がない部署です。ストレスを感じやすい部署の1つです。
他にも寄付金を集める部署なども大学によっては至上命題があるためストレスを感じやすいです。

おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
《おまけ》クレーム対応 大学職員は変な人多め
民間企業でも変な人はいると思いますが、割合で言えば大学職員もなかなか変な人が多いです。
いや、私含めて変な人しかいないかもしれません。
あるときクレームの電話が入りました。
よくあるクレームとしては、近隣の住人の方から「公共交通機関のマナーが悪い」「タバコを公園で吸っていた」など学生のマナーに関するクレームです。
今回も同様のクレームでしたが、ある大学職員が電話越しで
「私に言われてもわかりません。知らないです」
と平気で言ってました。
しかし管理人の大学では、これは決して珍しいことではなく年配のおばさまによくある光景でした。
自分が大学を代表しているという認識は薄いです。

\ ▼まずは求人を探してみる▼ /
おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
パワハラはある?
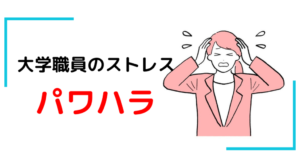
多くはありませんが、あります。
粘着質なものが多いです。
管理人の大学では、特に女性職員はヒエラルキーがしっかり存在しており、口には出しませんが内部での序列がはっきりしています(役職は関係ないです)。
序列が上の人から何か言われれば、間違っていても何も言えなくなる光景を何度も見たことがあります。
男性も嫉妬する人が多く、出る杭は打たれると言いますが、まさにその傾向が顕著です。
若く優秀な人は、根回し含めよっぽどうまく立ち回らないと潰されていきます。
もしくは一定の年齢になるまで、爪を隠して生きていくしかありません。

\ ▼まずは求人を探してみる▼ /
おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
うつ病になる?休職する人いる?
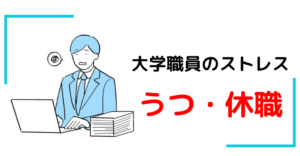
大学職員は外部に情報が漏れることは少ないため、あまり知られていませんが、それなりの割合でうつ病になる人、休職する人もいます。
正確にいえば、昔より増えてきました。
原因としては昔に比べ、大学職員の仕事も複雑化し、責任も多少なりとも負わされることが増えてきました。
そのため、昔の大学職員の雰囲気に慣れていた真面目な人(言われたことを言われた通りやる人)ほど、うつになり、休職していきます。
管理人の大学でも、10年前は休職しているのは数年で1人、2人程度でしたが、ここ2〜3年の合計は10人弱になりました。はっきり見せていないだけで潜在的な人も含めれば、精神的に問題を抱えている人は全体の1,2割はいます。
よく精神科に通っている人も見かけます。。。
ここは転職されてきた方も含めてという話になりますので、特にこれから転職される方は「人間関係」と「職場の暗黙のルール」にはお気をつけください。

\ ▼まずは求人を探してみる▼ /
おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
転職してきた人がストレスを感じたこと
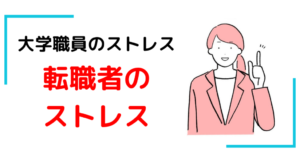
今までのはどちらかといえば生え抜き職員の話でした。
では転職者が大学職員になってストレスを感じたことはなんでしょうか。
管理人の大学と周辺の大学で転職してきた人に聞いた結果です。
1位「会議が会議でない」
何も決まらないけど、これ会議?というのが一番ストレスといってました。
特にびっくりするのが
・ぐだぐたと何時間もかけるのに決まることが1つもない
・責任の所在がない。特定の人に責任を任せることがないため、責任者不在。誰が責任者?
この2点とのことでした。
ちゃんと会議からの指示を行おうとしても、誰の言うことを聞いていいのかわからないと指示系統に困ることが多いようです。

おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
2位「人的ストレスが半端ない」
前の職場でも人的ストレスはあったけど、大学職員もハンパじゃないとのこと。
先に書きましたが、民間企業でちゃんと社会人をやってきた人ほど、大学職員の文化に馴染みにくいです。
大学職員は比較的簡単に「私に聞かれてもわからない」「私にはできない」と上司含め言います。
部下に仕事をお願いしても「難しくて私には無理です」と平気で断られます。
そのため時間をかけて丁寧に説明し、フォローもちゃんとすると約束を取り付けてどうにかやってもらいます。
また職員も教員もちゃんと話したはずなのに、返信がなかったり、そんな話は聞いていないといわれ、社会人としての常識が通用しないためストレスがたまると言ってました。

おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
3位「意欲を異常なまでにそいでいく」
これに関しては大学職員あるあるです。
転職者はやる気がちゃんとあります。
今までの経験からこうしたらいいのではないかと提案をよくしてくれます。
しかし大学職員は新しいことをやるときまず否定から入ることが多いです。
デメリット・リスクがどれだけあるかから考えます。メリットから考えられる人はレアです。
どれほどそのデメリット・リスクが自分に周囲に影響を及ぼすか考えます。
新しいチャレンジは提案者によっぽどの熱量がない限り成功しません。
もしうまく行ったとしても、責任の所在を曖昧にするために会議にかけます。
とても長い期間が必要になります。
そのため、以前の職場では流石にここまで説得の時間も、決まるまでの時間もかからなかったといってました。
またその間に、教員が絡むと更にやっかいなことになります。
さらなる時間が必要になっていきます。
そうなってくると、次からは「もういいや。適当にしておこう」と意欲がなくなっていきます。
大学職員はチャレンジによるメリットはあまり考えません。
デメリットがどれだけ大きいかを考える思考になっています。

\ ▼まずは求人を探してみる▼ /
おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
《大学職員へ転職したい方へ》
大学職員転職は情報戦
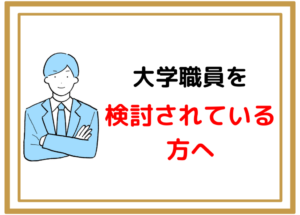
大学職員の転職は情報線です。
なぜなら大学はいつ求人が出てくるかわからないからです。
昨年は求人を出していても今年は出さないという大学も多数あります。

まずは大学職員の求人情報を逃さないようにすることが重要です。
昔は大学も縁故やハローワーク、大学に求人を出す程度でしたが、今は転職サイトをようやく使うようになりました。
そのため転職サイトは最低2つ以上登録しておくことをおすすめします。

今のあなたの置かれている状況で、登録する転職サイトを使い分けておけば大丈夫です。
CASE1
✔まだそこまで本気で転職を考えているわけではない
✔少し大学職員に興味がある程度
⇒求人が見れるリクナビNEXTやマイナビなどに登録しておけばOKです。
必要なときに求人を確認できます。
\ ▼まずは求人情報を探してみる▼ /
CASE2
✔本気で大学職員含め他業種も転職を目指している
✔転職のサポートも欲しい
⇒密に連絡をとってくれるリクルートエージェントなどエージェント系の転職サイトに登録しておくことをおすすめします。
特にエージェントは非公開求人を持っているので、情報を逃したくないときはエージェント系サービスがおすすめです。
また大学によっては求人期間がとても短いところもありますので、求人情報は常に入るようにしておきましょう。
\ ▼非公開求人多数!情報を逃さない!▼ /

おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
【おすすめ派遣会社】
▶マイナビスタッフ![]() ・求人数トップクラス!派遣のことならテンプスタッフ
・求人数トップクラス!派遣のことならテンプスタッフ
▼大学職員採用側の事情▼
-

【激ムズ?狭き門!?】私立大学職員への転職は難易度高そう!新卒・中途の倍率はどのくらい?転職難易度事情
「大学職員への転職って難しそう」 「倍率高そう」 そこで今回は といったことについて紹介します。 &n ...
続きを見る
まとめ
大学の業界研究に役立つ▼

大学職員のやっかいなところは、外部との交流がなさすぎること、思い切っていえば、新しいことを何もしなくても生活できるところがあります。
大学職員の中だけで完結した人生となります。
そのため新しい情報・文化を取り入れるということがありません。
結局凝り固まった考え方の人が増えます。
昔からある考え方が絶対となり、その学校の考え方にシフトしないと、ずっとストレスがたまってきます。

今回は大学職員の良い面ばかりをPRする人が多いため、あえて悪い面も記事にしてみました。
とはいえ、やりがいのある仕事も多数あるのが大学職員です。
人を育てる機関に勤めるというのは誰でもできることではありません。
学生のために、これから社会を創り上げていく人材のために何ができるのかを考えるのが大学職員だと思います。
熱い志を持っていれば大学職員になっても、ストレスに負けず生き抜いていくことができます。
どこの企業でもあるようなストレスは存在すると思っていただきながら入職していただいた方がいいです。
\ ▼まずは求人を探してみる▼ /
おすすめ転職サイト
【専任職員(正社員)を目指す】
▶リクナビNEXT・リクルートエージェント
転職の参考になれば幸いです。
記事を読んでいただきありがとうございました。